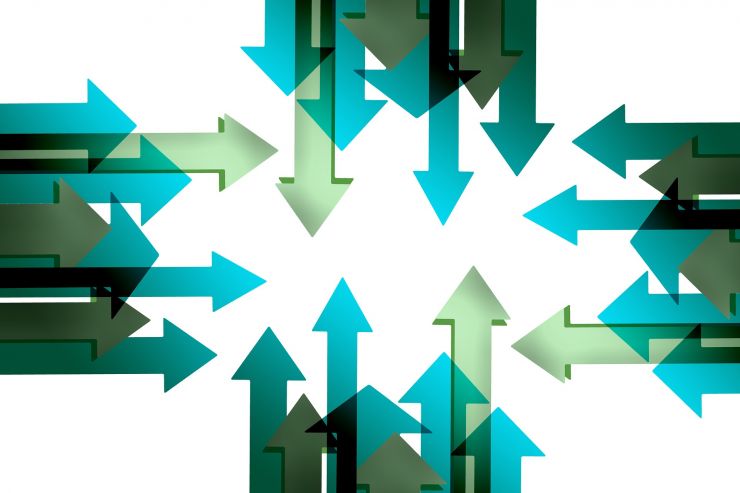SHIFT
SHIFTは、既存の事業領域や働くヒトたちをコアにして、製品・サービスのあり方を規定し直し、市場の新しい認知を得ることで事業価値を高める手法です。製品・サービスのあり方(ベクトル)を、どの方向に、どの程度の大きさでずらす(SHIFT)かが肝要であり、ベクトルの方向と大きさを小さくずらすだけなら、既存事業の周辺領域におけるイノベーションを創発できる可能性が高まります。なお、イノベーション創発手法にはもうひとつJUMPという手法もあります。こちらは、既存事業とはまったく縁のない事業領域や、現有のヒトとは違うヒトを新たに集めてイノベーション創発に取り組む手法です。SHIFTとJUMPを比較すると、SHIFTのほうが比較的リスクが小さいことは明らかであり、既存事業に大きな変更を加えることなく新規事業を創造したいと考える企業には、SHIFTを推奨します。
しかし、既存の事業領域で働く既存のヒトたちに新規事業創造を担わせることの難しさを忘れてはいけません。ひとつめのボトルネックは、イノベーション創発の働き方に対する無理解の壁です。イノベーションや新規事業創造にチャレンジするための最適な働き方は「リーン・スタートアップ」ですが、その特徴は、「ビジネスモデルキャンバス」で不確実な未来を切り拓く仮説を描き、製品開発と顧客開発を同時並行で進める「顧客開発モデル」というビジネスモデルを構築して、試行錯誤を繰り返しながら事業化まで全力疾走する「アジャイル」な仕事の仕方にあります。一方、既存事業で働くヒトの仕事の仕方は、「精緻な計画」に則って、製品開発を一歩ずつ進めていく「製品開発モデル」というビジネスモデルで、研究開発、製造、マーケティング、営業、サービスというビジネスプロセスごとに完結してから次のプロセスに引き渡していく「ウォーターフォール」な仕事の仕方です。相容れない2つの仕事の仕方を同じヒトに行わせることは無理です。ボトルネックのふたつめは、社内認知形成プロセスにおける拒否反応です。従来型の製品・サービスの企画、開発、製造、販売、サービスに携わっているヒトが、新商品に対してフラットな立場から評価できるのか、認知バイアスをどのように払拭するのか、また既存事業には厳格な業績責任が負わされているのに、新規事業は赤字でも仕方ないという名目でその責を逃れているという見方をするヒトもいて、世に問う以前に社内の合意を得られなくなってしまうのです。
また、SHIFTそのものが難解であることも否定できません。Blue Ocean Strategyも使いこなすことは簡単ではありませんが、SHIFTはさらに思考レベルの抽象度が高く、自分たちで思考の枠組みを自由に決められるがゆえに、より難しくなります。まったく新しいものを世に問うためのアイデアソンを徹底的に行って自分たちの思い込み(バイアス)を可視化したうえでそれを破壊し、問題の本質にフォーカスするプロセスを辿るのですが、デザインシンキングを使ったアプローチに慣れていない方にとっては簡単ではありません。
これらの点をクリアするには個人ごとに思考を突き詰め、議論の質を高めることが必要とはなりますが、SHIFTにはその苦労をするだけの価値があるイノベーション創発手法であることは事実です。製品開発モデルにおいてNo.1の称号を戴いた日本人の問題解決能力の高さはおそらく世界最高レベルにありますが、課題はその前段階にある問題設定能力の低さです。しかし、SHIFTで問題設定できるようになれば、持ち前の問題解決能力で次々とイノベーションを創発できるはずですし、それに続いてデジタルビジネスモデリングの構築に成功できると確認しています。
JTBD
例えば、TOYOTAが自動車メーカーからモビリティ・カンパニーへとトランスフォームしたのは、モータリゼーション・カンパニーという段階は既に達成したことであり、これからは、世界中の環境保全や、世界中の人間に等しく保障されるべき「移動の自由」という権利への貢献、人々が安心して安全に生きていくうえで必要な社会基盤の構築への貢献等をパーパスに掲げ、そこに至るまでにTOYOTAがなすべきことをジョブとして捉え直した結果です。「ドリルを買いに来た客が欲しいのはドリルではなく、穴をあけることだ」「朝にミルクシェイクを買いに来るドライブスルー客は飲み物が飲みたいのではなく、出勤途中の退屈しのぎのためだ」と実証されたことからわかるように、顧客がモノやサービスを買う理由はジョブを満たすためであって、モノやサービスを買うことが目的ではありません。ジョブにフォーカスして商品を開発することは、プロダクト・アウトのスタンスに立つ企業にとって簡単なことではありません。しかも、ジョブにフォーカスすればするほど、創業事業や主力事業における成功体験やヒット商品を否定することにもなりかねず、研究開発や製造部門から大きな反発を招くこともあるでしょう。まさに「イノベーションのジレンマ」に嵌り込む可能性があるのです。
しかし、JTBDのフレームワークを活用して検討を進めていくにつれて、視座が高くなり、視野が拡がり、既存事業の視点では捉えきれなかったジョブが見えてくるようになります。顧客の購買行動がモノからコトへと変化した理由が、まさにジョブを解決するためだったことの証左です。自社の商材は顧客のジョブを解決できているか否か、できていないジョブは何かを明確にするという切り口から、イノベーションを創発できる可能性を共に探りましょう。
N1 Analysis
N1分析は、予め分類された顧客層に属する特定の個人(N=1)を徹底的に分析して、各顧客層ごとに有益な施策を行うべきかを明確にする手法です。「予め分類された顧客層」とは、5つの階層からなる顧客ピラミッド(上から順にロイヤル/一般/離反/認知・未購買/未認知)のうち、最下層である未認知顧客を除く4階層をブランド選好(積極的/消極的)に基づいて更にふたつに分け、合計9つのセグメントに分類したものを指します。そして、各セグメントから実在する消費者を一人選び、徹底的に分析して、各セグメントごとに比較、それぞれが上位セグメントに移行するために講じるべき打ち手を明らかにします。
例えば、ロイヤル顧客を分析すれば、積極的一般顧客をロイヤル顧客に育てるための示唆が得られる可能性が高く、分析結果をフィードバックして新たなプロトタイプを造り、積極的一般顧客にぶつけて彼らのうちのどのくらいの割合が購買意向を示すかを定量的に把握、購買意向を示した人が多いものを全速力で仕上げて販売すれば、彼らがロイヤル顧客へと成長する可能性を拡げることになります。N1分析を各セグメントごとに実施すれば、それぞれのセグメントごとに「効く」打ち手を定量的に把握することができるわけです。一般的には、ロイヤル/一般顧客層への効果的なアプローチはロイヤル顧客の増加を、離反/認知・未購買/未認知顧客層への効果的なアプローチは新規顧客の増加をもたらすことになります。
これはCX(Customer eXperience、顧客体験)をCJ(Customer Journey、カスタマー・ジャーニー)のステップごとに最適化することに通じるアプローチでもあり、セグメント別のマーケティング施策を同時に検討できるという点では、JTBDより実務に展開しやすい特徴があります。その一方で、既存事業や既存商品の枠組みから完全に解き放たれて発想することは難しく、イノベーションというよりインプルーブメント(改善)の範疇での取り組みに陥りやすいことには留意が必要です。JTBDは顧客が解決を望む真の課題(ジョブ)にフォーカスすることから、既存事業や既存商品の枠にとらわれない自由な発想や予想外の発見や着眼点を見出せる可能性があるものの、ジョブを解決するソリューションの具現化フェーズになると効果的な施策をまとめ切ることが難しいのも事実です。JTBDでジョブを特定し、N1分析とCXデザインを組み合わせてマーケティング施策をまとめるというのが理想的ですが、クライアントの強みを考慮して取り組み方を定めましょう。
Other References